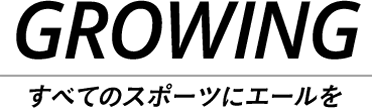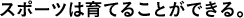インタビュー

インタビュー
希代の名スキーヤーが第二の人生を“スキーの未来作り”に捧げた理由
オリンピック4度出場の皆川賢太郎氏が振り返る競技人生
本格的なシーズンが到来したスノースポーツ。2022年の北京冬季オリンピック・パラリンピックを目指し、寒さを吹き飛ばすような熱い戦いが繰り広げられている。その舞台裏で、夢の祭典に4度出場した名スキーヤーが今、公益財団法人全日本スキー連盟の一員として第二の人生を送っている。皆川賢太郎氏。2006年のトリノオリンピックではアルペンスキーで4位入賞を果たした皆川氏は、なぜ、指導者でも解説者でもなく、連盟の1スタッフとして競技の普及・発展に尽力しているのか。競技生活を振り返りながら語ってもらった。
小学4年生で競技を始め、ジュニア時代から世界のトップで活躍すると、17歳でプロに転向。以来、ワールドツアーを回り、世界を股にかけて戦った。「公にしている手術は2回だけど、本当は5回した。プロ選手なので、怪我を明かすと商品価値がどんどん下がってしまうから」と打ち明けた過酷な競技人生。良い記憶と苦い記憶。どちらの方が色濃く残っているのか。そう問うと、独特の言い回しで振り返った。
「今、俯瞰的に見ると、スポーツは“人生が見える”から、すごく面白いと感じます。一般社会では、普通は65歳で定年を迎える時に自分の哲学みたいなものが生まれると思う。でも、競技人生では、20代前半は自分に与えられた能力、可能性、時間は無限なのではないかと思い、20代後半から30代にかかると次の若い世代が出てきて競技人生の終点が見え始め、延命する作業に変わり、やがて引退を迎える。そういう中で人生を1回、疑似体験できて自分の哲学を一度見いだせる、良い仕事だったなと。嬉しい、つらいという感情は競技にかかわらず、人生に必ずあるもの。それ以上に凝縮した日々を送れたことは良い体験でした」
人生そのものを味わったという競技生活。「定年」に置き換えられる引退を迎えたのは2014年、37歳の時だった。プロとして送った20年を通じ、得た「哲学」とは、いったいどんなものなのか。
「一番大事にしたのは『ずるい選択をしない』ということ。物事を天秤にかけ、取捨選択をしなければいけない時は必ずある。その時、人生の主人公である当事者がずるい選択、つまり簡単に手に入るようなものを選んだ場合、その効果は一時的な瞬発力はあるけど、永遠に続くものではない。ずるい選択をしない方が能力を得られ、蓄えられていくことを学べると思います」
競技人生は挫折と決断の連続だった。そうして着実に成長を続け、1998年長野大会でオリンピックに初出場。足掛け12年で実に4度も夢の舞台に立った。なぜ、長く第一線を走り続けることができたのか。
「僕にとっては辞める方が怖かった。怪我をした時、何度も引退を考える瞬間はありました。でも、(引退を)選択しなかった理由は『日本代表の皆川賢太郎です』と言えていたものが、辞めた瞬間から自分が何屋さんなのか、わからなくなる。没頭してきた道から外れ、『あなたは何屋さんなの?』と言われた時、返せる自分がいないことの方がよっぽど怖かった。自分が培ってきた知識、経験、時間をできる限り長く続けることしか頭にありませんでした。そういう中でオリンピックを意識したことで、自分の未来のレールもどんどん伸びていったと思います」
現役を続けるエネルギーとなったオリンピック。最も印象的だった大会には、4位に入賞したトリノ大会を挙げる。しかし、2010年バンクーバー大会が最後となり、2014年ソチ大会を目前にした37歳で引退を決断した。
「一番の理由はもう能力がなくなったということ。最終的には(選手として)目が見えなくなりました。何のスポーツでも1秒が10分割に見えるか、100分割に見えるかで景色が変わってしまう。段々と自分が速いと感じたものが速くなかったり、誤差が生じるようになり、これが衰えかなと感じたので、辞めようと決めました」
41年ぶり新潟県苗場開催アルペンスキーワールドカップ誘致の舞台裏

スキー板を脱ぎ、迎えた第二の人生。競技の傍ら、32歳から飲食業で起業しており、経営者の道もあった。しかし、本腰を据えたのは全日本スキー連盟に入り、競技の普及・発展に尽力すること。決断の背景には現役時代のある経験が関係していた。
「自分は日本代表を3回辞退している。日本のスキー界のルールに疑問を感じることもあり、当時、自分は正しいと思って競技の普及・発展を目指す選択をした。大きな組織でもっと良くできると感じたこともあった。現役を辞めた時、自分と同じ思い(もっと、スキー競技をメジャーにしたいという思い)をしている選手がいるのではないかと自分に問いかけた。実際にそういう人もいました。トップレベルでは競技を続けるより、早くに辞める人の方が圧倒的に多い。選手たちにとって正しいサポートがまだ足りないと思いました。それを改善するには、ルールを整備できる側にいかない限り難しい。上流から物事をきちっと変えないと、現場の一つひとつの問題を解決できないと思いました。そういう考えのもと、今も仕事に取り組んでいます」
現在は常務理事に加え、競技本部長も兼務しており、2つの重責を担う。マーケティングと競技力の向上という異なる課題に腐心。その中でも大きな成果の一つとなったのが、2016年の「Audi FIS アルペンスキーワールドカップ2016湯沢苗場大会」の誘致だった。
日本では、2006年の長野・志賀高原以来10年ぶりの開催。新潟・苗場スキー場は1973年にワールドカップが日本で初めて行われた歴史もあり、当地開催は1975年以来、実に41年ぶりのこと。しかも、皆川氏が小さい頃に汗を流したスキー場でもある。「アルペンレーサーのDNAはここにある」という原点の場所。アルペンスキーを国内にアピールする絶好の場として心血を注いだ。
「海外も含め、スキーの競技比率はアルペンが圧倒的。日本はシニアも入れると、競技人口はジャンプの350人に対して、アルペンは9,000人。競技がメジャーかどうかは別として、日本以外でも世界中がそうなっています。どうやってスキー界を活性化させ、選手人口を増やし、育成していくのか。効果的なことはワールドカップをやることでした。アルペンスキーは日本ではまだそこまでメジャーな競技ではないけど、大会を誘致することで将来的に構造が良くなるという背景もありました」
当初は知名度を買われ、大会アンバサダーを打診された。しかし、「客寄せパンダになっては意味がない」と固辞し、自ら志願して敢えて事務局員を買って出た。「全体の会議は一番後ろでパイプ椅子に座っていた」と笑って振り返る。だからこそ、大会をゼロから作り上げる段階から尽力し、実現にこぎ着けた感動は忘れられない。
「大会2日間で1万8,000人のお客様に来ていただき、その中に子どもたちもたくさんいました。実際に『ワールドカップを目指したい』という子どもの声も届いた。それはすごく嬉しかった。学びがある一方で反省も山ほどありました。これを打ち上げ花火で終わらせず、定期的にどう開催していくのか。感動を得ながらも、反省することの方が多かったですね。継続できる仕組みを今も模索しています」
自身はもちろん、日本スキー界にとっても大きな財産をもたらしたワールドカップ。大会開催の舞台裏で支えになったのが、スポーツくじ(toto・BIG)の収益による助成金だった。皆川氏も「後押しの大きさをすごく感じた」と振り返る。アルペンは規模の大きさゆえ、大会開催に多くの資金が必要だった。
「世界最高峰」を見せる以上に大事なワールドカップの価値

「例えば、ワールドカップに関してモーグルは1大会で5,000万円、ジャンプは4,000万円弱で開催できます。ですが、当時のアルペンは3億4,000万円の事業。世界から30か国の選手が出てきて、日本にもこのくらいの競技人口がいるからと訴えても、日本のスポンサーにはなかなか響きませんでした。そうなると、大会開催のためにはこういった助成金(スポーツくじ)の支援がないと実際には難しかったですね」
スポーツくじの収益による助成金は、Audi FIS アルペンスキーワールドカップ2016湯沢苗場大会の開催に役立てられ、その助成金額は7,000万円以上にのぼった。
2020年には苗場スキー場で、4年ぶりのワールドカップ誘致に成功(Audi FIS アルペンスキーワールドカップ 2020 にいがた湯沢苗場大会)。さらに魅力的な大会を目指している。これを機に、産業として日本のスキー文化を発展させるという大きな狙いもある。
「次なるレガシーとして求めるのは、誘致した後の展開。今は日本全体で、国のインバウンド観光事業としてのスキーの需要が高まっている一方で、学校の教育プログラムにおけるスキー授業は減っています。そうなると、国内ではスキーに対する親しみが減る中で、海外から多くの人が日本にスキーをしに来たとしても、スキーの環境下で働く人がいなくなってしまう。ワールドカップをやりたい背景には、『世界最高峰の大会を持ってきたい』ということはもちろん、それ以上に大事なのは教育と産業に関わる人を創出したいということです。だから、こういった世界大会は必要ですし、やっていくべきだと思っています」
また、日本で観戦・体験できる世界最高峰の大会。皆川氏は日本の次代のエース候補の呼び声高い25歳・成田秀将選手に加え、2016年の岩手国体少年の部優勝など注目を集めてきた19歳・若月隼太選手、ジュニア時代から世界を転戦して戦ってきた20歳・加藤聖五選手を注目選手に挙げる一方、世界で勝てる選手の長期的な発掘育成の必要性も感じている。
「大会の環境と設備は前回の反省を生かして良いものを作れますが、最も難しいのは日本のスターを作ること。アルペンスキーは世界的に競争率も高い。そんな中で、日本開催で活躍できる日本人のスターが欲しい。お金を出せば強化は何とかなるわけではなく、スターを買えるわけでもない。自分たちで育てないといけない。2020年(アルペンスキーワールドカップ)、2022年(北京冬季オリンピック)まで優勝争いをするプレーヤーが欲しいですし、その先に向けても重要だと考えています。競技本部長として地道な作業になりますが、大会の魅力と選手の実力が掛け算になると本当の影響力になります」
ファンを呼べる実力のある選手の育成へ――。連盟では「アルペン競技タレント発掘育成事業」(スポーツ振興くじ助成事業)というプログラムで金の卵の発掘・育成にも挑戦。その価値の大きさについて、興味深いデータを交えながら明かした。
「ユース世代で世界大会を経験していない選手はシニアでオリンピックのメダルを獲得できる確率は低いと言われています。実際、メダリストはユース世代で世界ランク3位以内にほとんどの選手が入っているというJOC(日本オリンピック委員会)の統計が出ている。僕はジュニアで19歳まで世界ランク1位でした。ユース時代に世界ランク1位でないと世界チャンピオンになることは難しい。そういったところでプログラムを通じて、実力のある選手を育てていくことはとても大事だと思っています」
目先の結果だけではなく、10年、20年後のメダリストを発掘し育てていく。さらに冬季国体の開催や、スキー場におけるリフト等の整備も競技の未来につながっていく。こうした選手の発掘育成事業や冬季国体の開催支援及び競技会場の整備、スキー環境の整備にもスポーツくじの収益による助成金が役立てられている。
「何でも独自資金だけでやることは難しい。莫大なお金がかかり、多くの連携も必要になる。だからこそ、スポーツくじのような助成金が全国で使われるのは、すごく大事なこと。スキー選手を志す全ての子どもたちに対して、育成費を分配していくほどの体力は連盟にはありません。国際大会を誘致して世界というものを知ってもらうことで『オリンピック選手になるんだ!』と子どもも思ってくれる。スポーツくじができて非常にありがたかったのは、国民がスポーツくじを通じてスポーツに参加したエネルギーが競技の普及・発展に生かされるようになったこと。だから、日本のスポーツの成長は今、スピード感を増していると思います。実際、初めて出場した長野オリンピックの時はまだまだそういう段階ではありませんでしたから」
「スタートは独りで切る」―改めて今思う、スキーの魅力

スキーの普及・発展に駆け回る日々。行動の根底にあるのは“スキーが人を成長させてくれる”という思いだ。あらためて今思う、競技の魅力とは何なのか。
「スノースポーツの良いところは季節が限られていること。これは人間が絶対コントロールできない部分です。限られた時間の中で楽しむ良さを知ってもらいたいですね。そして、アルペンスキーで僕が最も好きなのは『スタートは独りで切る』ということ。スタートをする時、どんな急斜面でも自分の意思で踏み出さなければいけないですし、誰も助けてくれない。そこに己を知るという良さが生まれる。スタートでコールが鳴って出る瞬間、自分自身が緊張や不安と向き合わないといけない。そういうスポーツとしての魅力が僕は好きです」
日本では最大1,860万人いた競技人口は現在、700万人を割り込むほど、落ち込んでいる。「しかも、700万弱の競技人口のうち、SAJ会員登録(全日本スキー連盟が運営する会員組織)をしていただいているのは100分の1ほど。つまり、何か目的を持ってスキーをしている人がその程度しかいない」と話し、いかに競技としてのスキーに魅力を感じてもらうか、という重要性を痛感している。
「競技人口を増やして普及していく作業も大事だけど、現状の700万人のスキー競技者が自分たち(全日本スキー連盟)のプラットフォームに入ってもらうことがさらに大事。その方々に2回、3回とスキー場に足を運んでもらうこと。産業としては非常に可能性を持っているから」と言う。では、どんなスキーの未来像が理想なのか。「言い過ぎと言われるかもしれないけど、本当のことを言うと……」と、胸に秘めた壮大な夢を明かした。
「中国は国策(2022年北京冬季オリンピック)としてスキー・スノーボードの競技人口3億人を目指している。日本は(競技人口が)1,860万人いた時代、最大700か所あったスキー場がオーバーフローしていました。現在、スキー場は約400か所で実際に稼働しているのは280か所くらいです。天然雪が降らない隣国で3億人に増えた時、日本の観光の受け入れはどうなるのか。そう考えると、日本で最大だった『1,860万』は大きな意味を持つ数字ではない。一方で日本の選手強化を考えると、今の強化資金8億円が倍の16億円になったら使い切れないくらいで、選手たちが満足できる金額は分かっている。ただ、満足できる環境の整備を実現するには産業として発展して、お金を生み出さないといけない。だからこそ、産業が競技と循環していくことが理想です」
中国の競技人口が爆発的に増える可能性があり、日本に対する観光需要の高まりが期待される中、目指すべきは「1,860万」より大きな受け皿を用意して環境を整備すること。こうして、産業としてうまく回っていけば、競技としての強化資金も増えていく、と皆川氏は考えている。
「そのために『スタジアム』が絶対必要だと思っています。僕が思う形はスキー、スノーボードが年中できるドーム型施設。昔あった『ザウス(屋内スキー場)※』のような施設が海外では39個目ができている。日本ではバブルの産物と思われていますが、世界にそれだけの数の施設があり、収支が取れている。日本のような先進国なら(通年でスキー・スノーボードができる施設が)1つはあった方がいいと考えています。スキー道具を10万円で揃えたとしても1年の間で3か月しか使えないのはもったいない。そういう部分を解消する意味でも必要だと感じます。もちろん、今の時代はアーティストのコンサートができるようなアリーナも必要で、興行ベースで検討していかないと収支が取れない。どうやってスキードームを作っていくかが僕の夢です」
日本のスキー界に対し、雪を溶かすほどに熱い思いを明かしてくれた皆川氏。自身は今後、どんな未来を築きたいのか。
「僕は雪にまつわることに関わっていければ、他に求めることは特段ありません。僕らスノースポーツの人間は、雪の上に立って初めて存在価値がある。次に携わる子ども、選手、産業があるから自分たちが残したものを振り返ってもらえる。徹底して雪のことをやるのが使命。それだけで僕は十分、幸せ。特段、自分が何かになりたいとは思っていないから」
現役時代のように今なお、トップスピードで日々を駆け抜けている。その先に、スキーの明るい未来があると信じて――。

※「ららぽーとスキードームSSAWS(ザウス)」
1993年7月~2002年9月まで千葉県船橋市で営業していた屋内スキー場。
SSAWSとは「Spring」「Summer」「Autumn」「Winter」「Snow」の頭文字からきており、当時「世界最大の屋内人工スキー場」として長さ490メートル、高さ100メートルのゲレンデであった。

皆川 賢太郎みながわ けんたろう
1977年5月17日、新潟県出身。小学4年生からアルペンスキーを始め、17歳でプロに転向。1998年長野大会からオリンピックに4大会連続出場し、2006年トリノ大会で4位入賞。2014年に引退し、全日本スキー連盟常務理事に就任。2016年、アルペンスキーワールドカップ実行委員会副委員長に就任。2017年から公益財団法人全日本スキー連盟強化部門トップとなる競技本部長を務め、スキーに留まらずスノースポーツ産業全体の発展に尽力している。
アンケートにご協力ください。
本記事を読んで、スポーツくじ(toto・BIG)の収益が、日本のスポーツに役立てられていることを理解できましたか?
スポーツくじ(toto・BIG)の取り組みに共感できましたか?