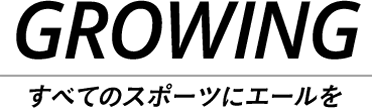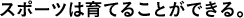インタビュー

インタビュー
「生きている世界は障がい者も一緒」 元Jリーガーの価値観を変えた挑戦
Jリーグを連覇した名守護神が「ブラインドサッカー」に挑戦した理由
2017月2月。Jリーグで優勝を経験した名守護神が「ブラインドサッカー」に挑戦し、話題を呼んだ。ゴールキーパー(GK)榎本達也氏。横浜F・マリノスで2003~2004年シーズンの連覇に貢献するなど第一線で長年活躍し、FC東京に在籍していた2016年限りをもって37歳で引退した。直後に発表されたのは、ブラインドサッカー選手としての“復帰”だった。
ブラインドサッカーは、視覚障がい者が行う5人制サッカーのこと。試合時間は前後半各20分の計40分間で行われ、フィールドプレーヤーはアイマスクを着用し、音の出るボールを使ってプレー。得点で勝敗を競う。ただ、多くのパラリンピック競技と異なるのは、GKに限っては視覚障がいのない者のプレーも可能で、障がい者と健常者が一緒にプレーできることが特徴の一つだ。
そんな競技への挑戦のきっかけは、意外な誘いにあった。
現役引退を決めると、FC東京から普及部のスタッフとして打診があり、快諾した。しかし、重なるようにしてブラインドサッカー日本代表の高田敏志監督からも声がかかった。「ブラインドサッカー、どう?」と。最初は「コーチをやってほしいのかな」と思ったという。しかし、実際に伝えられた言葉は「選手としてやってほしい」だった。
「まさか、そんな風に声がかかるとは……」と驚いたオファー。ブラインドサッカーというスポーツがあることは知っていたが、ルールを知っているわけでもない。ましてFC東京のサッカースクールでコーチをすることも決まっていた。それでも「一度、雰囲気を感じてほしい」と熱意に押され、行ったのは2月の日本代表合宿。そこで、練習に参加をしてみた。
「やってみたら、これが予想外に楽しかったのですよね」
味わったのは思ってもみない興奮だった。ピッチは縦40メートル×横20メートルと、Jリーグでプレーしていた頃と比べると半分以下。しかし、アイマスクをつけた選手がまるでボールが見えているかのように強烈なシュートを放ってくる。自分が経験したことのないサッカーとの出会い。「新しいおもちゃを与えられた子どものような純粋な楽しさだった」という。
だからこそ、迷った。挑戦するとなれば、選手とスクールコーチとの二足のわらじを履くことになる。「もともと器用じゃない。一つ決めたらのめり込むタイプ」と自分で認める一本気な性格。中途半端なことはしたくない。
決め手になったのは、スクールで小学生たちに自分が伝えている一つの言葉にあった。
「現役時代もチャレンジはずっとしてきました。だから、子どもたちには『できないからやらない』じゃなく『できないかもしれないが、一度やってみよう』と伝えていた。スクールコーチとブラインドサッカーの選手を並行してやっていくことは難しいと後ろ向きに思っていた。でも、子どもたちを前にしてチャレンジしていない自分がいるなって……」
教える子どもたちに嘘はつきたくない。高田監督に伝えた答えは「やります」だった。
戸惑ったブラインドサッカーのGK「今までの常識にとらわれてしまう」

こうしてスタートした「ブラインドサッカー選手・榎本達也」の道。
Jリーグの第一線で活躍したGKなら、簡単にプレーできるのでは? そう思ってしまうかもしれないが、実際には難しさがあった。一番はルールの違い。「プレーエリアが決まっていること」だ。GKがボールに触れられるのは、ゴール前の長方形エリア内(縦2メートル×横5.82メートル)だけ。声でコーチングできるエリアも決まりがあった。
「エリアから出てしまうと即ファウル。PKを与えてしまう。プレーの制限が一番難しく、戸惑った」
当然、GKとしての基礎となるレベルは高い。「技術的にキャッチ、止める、声をかけるという部分はもちろん、Jリーグでやってきた選手として利点はあった」というが、フィールドが狭い分、シュートは2~3メートルの至近距離からバンバン放たれる。しかも、アイマスクをつけてプレーしている相手。対峙すると、今までにない感覚だった。
榎本氏は「彼らはGKを見てタイミングを取ることがない。だから、GKは動きを読みにくい状況であっても止めないといけない。目が見えているからこその難しさがあり、今までの常識的な動きにとらわれてしまうことが難しかった」と語る。視界がない相手と向き合い、得点を防ぐ。これも健常者がプレーできるブラインドサッカーの魅力の一つだ。
目が見えない選手とチームメイトになる。その点においては「伝え方」も変わってくる。まずはサッカーをプレーする時と同様、選手の性格を掴み、「この選手は強く言っても大丈夫、この選手は声のトーンを抑えよう」と工夫。プレーに入り込みすぎると指示が聞こえなくなる選手には声をかけるタイミングも意識したが、それだけではない。
「高田監督が目指していたサッカーは“細かい”。『選手の立ち位置一つで失点につながる』というデータをもとに戦術を組み立て、立ち位置のたった1メートル、30センチの距離のズレとか、味方との距離はどのくらいに保つとか、そういう細かい単位にまでこだわっている。どのタイミングで、どんな言葉で伝えるかはGKとして苦労していました」
合宿に定期的に参加し、日を追うごとに理解を深めていったブラインドサッカー。パラスポーツの競技者として、障がいを持つ人たちと一緒にプレーすることには、驚きが大きかった。
「特に何の偏見もなく、まっさらな状態で入ったからこそ、逆に『凄い』しか感じなかった。見えていないのに走って、見えていないのにボールを蹴って、止められて……。ピッチのサイズもわかっている。そういった能力は自分より遥かに優れているなと。繊細さもそうです。ただただ驚きの連続でした」
長年サッカーをプレーしてきて、40歳を前にして刺激ばかりの日々だった。そのようにして“もらうもの”が多かったチャレンジ。しかし、榎本氏自身が“与えたもの”ももちろんある。
課題だった「プロ意識」、アジア選手権完敗の夜にぶつけた“本音”

課題として感じていたのは、選手たちの「プロ意識」だった。
選手が取り組む姿勢について「凄く純粋にサッカーをプレーするし、純粋に自分を高めようとしている。ちょうど小学生を指導していたので、彼らの前向きな姿勢と全く変わらない」と向上心を感じ取った。しかし、その一方で「言い方を変えると、勝負事に疎いというか、負けても悔しがらないというか」と物足りなさがあったという。
「『なぜ、負けたのか』というところにフォーカスすることが、なかなかできなかった。『今日は何が悪かったのか』『俺のプレーはこうだった。でも、負けてしまった』『それはなぜだったのか。何が足りなかったのか』というところに意識が及んでいかない。代表とはいえ、勝負事の肝のところを話す事が必要だと感じました」
忘れられない記憶がある。榎本氏が合流した2017年の12月。初の国際大会となるIBSA(国際視覚障害者スポーツ連盟)ブラインドサッカーアジア選手権2017に挑んだ。
舞台は東南アジア、マレーシア。実力を試す絶好の機会となったが、過去最低の5位と完敗した。「メダル獲得」を目標にしている東京パラリンピックへ向け、限られた強化時間の中での外国勢との対戦で、ゴールマウスを守った守護神は「貴重な機会をいかに大切にできるかという大会で甘さを感じた」と痛感した。
5位が決まった日の夜。ここで言わなければ、変われないと感じた。全員が集まったホテルのミーティングで立ち上がった。心の底からの本音をぶつけた。
「負けたのは、試合に出ていた俺の責任もある。でも俺の責任でもいいけど、そんな慣れ合いでぬるま湯に浸かっているような奴らとはサッカーをやりたくない。俺が辞めるか、お前らが辞めるかどっちか、だ。俺が辞めるのは構わない。俺の目的はみんながパラリンピックでメダルを獲って、その後にブラインドサッカーが発展していくこと。そのために少しでも自分の力が加わるなら、いくらでも助けるけど、今のお前らとだったら、何も成し遂げられる気がしない」
耳をふさぎたくなる選手もいたかもしれない。しかし、榎本氏は「変わってほしい」と誰よりも願っているから、敢えて厳しい言葉を投げかけた。効果は、確かにあった。以降、合宿を含め、選手同士で話し合う姿を目にする機会が増えた。「選手個々に少なからず変化があり、刺激になってくれたかなと思う」と嬉しそうに振り返った。
榎本氏に「自分がブラインドサッカーに残せた物は何だったか」と聞くと、「対話」という言葉が返ってきた。
「一つひとつのプレーでもそうだけれど、自分の意見を伝えるし、相手の意見も聞く。受け入れるし、要求もする。でも、要求するからには自分がやらないと、本当の意味で相手には伝わらない。それは、かなり言ってきたつもり。Jリーガーの頃から、そこが一番の自分の持ち味と思っていたので、それが彼らに少しは残っているといいなと思っています」
Jリーガーとして大切にしてきた「対話」。それが「ブラインドサッカー選手・榎本達也」が残したものだった。
「生きている世界は障がい者も一緒」―挑戦して変わった“価値観”

榎本氏は2019年1月の合宿を最後にブラインドサッカー日本代表の活動を退いた。
FC東京普及部のコーチ業のため、以降の参加が限定的になることから、東京パラリンピックでのメダル獲得の想いは仲間たちに託した。しかし、全力で駆け抜けた2年半。当初は迷いながらもチャレンジしたから、得られたことがある。
「価値観が変わったこと。まだまだ健常者の中には障がい者に隔たりを持っている人もいる。僕も彼らと出会わなければ、そう思っていた一人だったと思う。目が見えない人も耳が聞こえない人も、障がいがあることが不幸で、目が見える、耳が聞こえる健常者が幸せかという話ではない。私たちは壁にぶち当たるし、心が折れそうになることもあるし、怒ったり悲しんだり、いろんな感情がある。
それは目が見えないからといって、彼らも変わらないということ。『目が見えない』というだけで、生きている世界は一緒。普通に生活をし、喜怒哀楽があり、その中で彼らの世界にもスポーツがある。目が見えないから、ルール上はブラインドサッカーという形になるだけ。何も変わらないのだなと気づくことができました」
伝えたいのは「同じ世界を生きている」ということ。日本代表の同僚だった川村怜選手から言われた言葉がある。「目が見えないけど、ブラインドサッカーでプレーしている時が一番、自信がある。あのピッチは僕にとっての自由だから」。ああ、なるほど、と思った。「自分たちの世界の中でしか考え方の物差しを持っていなかった」と気づいた。
元Jリーガーが第二の人生に没頭したブラインドサッカー。そんなブラインドサッカーを楽しむための環境の整備をはじめ、パラスポーツの普及・発展にスポーツくじ(toto・BIG)の収益による助成金は役立てられている。今後に向けた課題を榎本氏に聞くと、リーグ戦も活発に行われるブラジルなど強豪国とのプレー環境の差を挙げた。しかし、それ以上に求めたのは、日本で「パラスポーツ」への意識が変わることだ。
「目が見えなくても、ブラインドサッカーをやる人もいれば、別のスポーツをやる人もいる。だから、僕としてはブラインドサッカーだけが盛り上がってほしいわけではなく、その世界(パラ競技)で自分を高めている人がたくさんいることを知ってほしいということが一番。例えば、今まで自分も日常的に周りを見て歩いているつもりだったけど、競技を始めると、とても多くの人が白杖(視覚障がい者が歩行時に持つ杖)を持っていると気づかされた。
その中には困っていそうな人も見るし、何事もないように私たちと変わらない生活を送っている人も見る。目が見えない人だけではなく、耳が聞こえない人も、車いすを使っている人も生きている世界は同じということ。それを知ってほしい。ブラインドサッカー自体、両者が共存し、競技が成り立っている。彼らもいろんな感情を持っていると、やってみて感じたからこそ、多くの人に気づいてもらいたいですね」
障がい者に対する理解が進むこと。それが、パラスポーツの盛り上がりに最も欠かせないものと、信じている。
観戦の楽しみ方は「目をつぶってプレーを見ること」
かつて一緒にプレーした仲間たちは、1年延期となった東京パラリンピックでメダル獲得を目指す。
ブラインドサッカーのGKとして「足りないものばかりだった」と振り返るほど、競技の奥深さを感じた榎本氏。実際に観戦してみると、様々な魅力が隠されている。選手以外で声をかけていいのはサイドフェンスの外側にいる監督、敵陣ゴール裏にいるガイド(コーラ―)の2人。選手は転がると鳴るボールの音を頼りに動くため、観客はプレー中に歓声を上げてはいけない。
最後に、競技を体験したからわかる楽しみ方を教えてくれた。それは「目をつぶってプレーを見ること」だ。
「ボールがどこに行って、どう動いているのか。想像しながら目を開けてみると『えっ、そんなところにあったの?』と発見ができる。何よりコンタクトプレーが多いし、それぞれ声をかけていい場所も限られている。そんな中でどういう声で指示を出しているのか。ぜひ、そういう楽しみ方をして、ゴールが決まった時には大いに喜んでほしい」
ブラインドサッカーに対する想いを熱く語った榎本氏。アジア選手権で敗れた夜、選手たちに「俺の目的はみんながパラリンピックでメダルを獲って、その後にブラインドサッカーが発展していくこと」と言っていた。「ブラインドサッカー選手」として戦った2年半。異例といわれた挑戦が芽となり、やがて花開く日をずっと、待っている。
(リモートでの取材を実施)

榎本 達也えのもと たつや
1979年3月16日生まれ、東京都出身。兄の影響で小学1年生からサッカーを始める。浦和学院高等学校(埼玉)を経て、1997年に横浜マリノス(現横浜F・マリノス)に入団し、2003、2004年のJリーグ連覇に貢献。世代別日本代表ではAFC U-19選手権準優勝、 FIFAワールドユース選手権準優勝。2007年にヴィッセル神戸に移籍。以降は徳島ヴォルティス、栃木SC、FC東京でプレーし、2016年限りで引退した。Jリーグ通算290試合出場。2017年から2年半ブラインドサッカー日本代表としてプレー。現在はFC東京普及部でサッカースクール、明治大学サッカー部でコーチを務める。
アンケートにご協力ください。
本記事を読んで、スポーツくじ(toto・BIG)の収益が、日本のスポーツに役立てられていることを理解できましたか?
スポーツくじ(toto・BIG)の取り組みに共感できましたか?